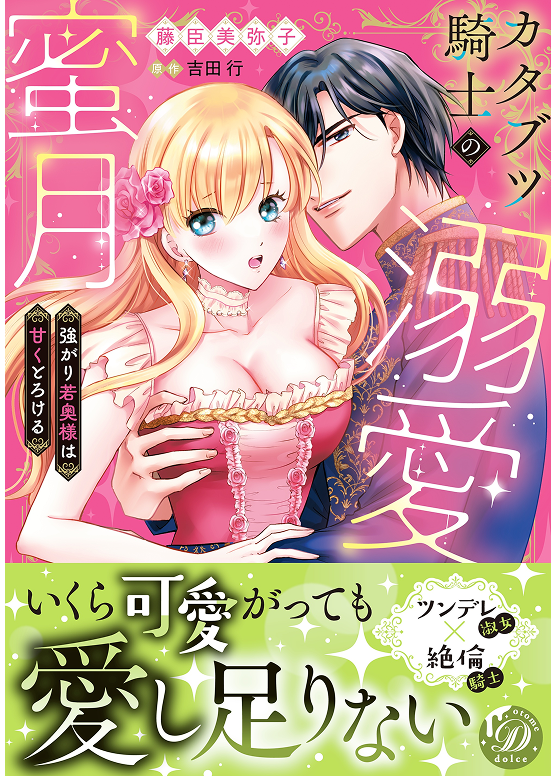-
試し読み
彼の腕の中でリュシエンヌはただ声を殺してうめくことしか出来なかった。
そんな彼女の様子を見てテオドールは少し動きを緩める。
「すまない、乱暴だったか? 痛くはないか」
どこも痛んではいない。むしろ彼の強引さに流されてしまいたい――こんな気持ちをどう言い表せばいいのだろう。
「……ばか」
結局憎まれ口になってしまう、こんな自分が嫌いだった。
テオドールは少し開いた彼女の唇に何度も口づけをすると優しく髪を撫でる。
「ようやくお前と夫婦になれて気が急いてしまった……ゆっくりするから許してくれ」
彼の唇が首の横を擽る。浅い戦慄が肌に拡がった。
「ああ……」
豊かに膨らんだ胸を優しく揉まれた。すでに固くなっている先端は彼の掌を刺しているはず……そこを刺激されるたびに声が大きくなってしまう。
「あん、ああ……」
触れられるだけでこんなに感じてしまう、でもそれを知られたくない、ふしだらな女と思われたくない――。
(でも、こんなの我慢できない)
彼の唇がとうとう胸の先端に触れた時、リュシエンヌの唇から激しい呼吸があふれ出た。
「ひ、あああ!」
優しく突起を摘ままれただけなのに、信じられないくらい感じてしまう。快楽がそこから全身に回って支配される。
「気持ちいいか? 良かった、もっといい声を聞かせてくれ」
「やあ……これ以上……」
感じすぎて、理性をなくしたらどうしよう――リュシエンヌは細い手で彼の体を押しのけようとした。だがそれはテオドールの欲望をさらに煽ることになった。
「可愛いよ、リュシエンヌ……昼間のお前は獅子のように強いが、ベッドでは子羊のようだな」
そして両方の乳房をぐっと中央に寄せると、二つの突起を同時に舐め始めた。耐えきれない快楽にリュシエンヌの唇から悲鳴のような声が出る。
「ひゃうっ、だめえっ!」
ぬるぬると擦られる刺激に感じやすい突起は赤く腫れあがり、さらに固くなっていく。テオドールはそれを指で摘まむと何度もしごいた。繰り返される淫靡な快楽にリュシエンヌは気が遠くなりそうだった。
「あん……もう……」
ぐったりと横たわる彼女の肩にテオドールは優しくキスをした。
「可愛い私の子羊、信じられないくらい柔らかいよ。全て食べてしまいたい」
彼の手がゆっくりと足を開いていく、とうとう彼を受け入れる時が来た――リュシエンヌは覚悟を決めた。
だがテオドールは足の間に体を入れると、そのまま顔をそこへ近づけていく。思わず足を閉じてしまったので彼の固い顔を挟んでしまった。
「な、なにをするの?」
男女のことについてなにも知らないわけではなかった。アンベール夫人のサロンに出入りしていたので普通の娘よりは耳年増かもしれない。それでもそんな行為は聞いたことがなかった。
テオドールは細い腿を押し拡げながら言った。
「抵抗しないでくれ。これはお前を傷つけないためだから、恥ずかしがらずに身を任せてほしい」
そう言われても、足を大きく拡げてそこを彼の目に晒すなんて耐えられなかった。恥ずかしさのあまりリュシエンヌは顔を覆って悪態をつく。
「ああ、なんてこと、この野蛮人! 信じられない!」
彼の大きな手に腿を掴まれ、とうとうそこを拡げられてしまった。そのすぐ傍に指がかかり、中まで開かれる。リュシエンヌは心臓が破裂しそうだった。
(私の体を調べているのかしら?)
本当は自分の純潔を疑っているのか、だからこんな破廉恥なことをするのだろうか――強気な言葉とは裏腹に心は不安で満ちていた。
「美しい」
だが彼の言葉は賞賛の驚きに満ちていた。
「女性の体をはっきり見たのは初めてだが、こんなに美しいものだったのか――綺麗な色で、触れたら壊れそうだ」
その言葉を聞いてリュシエンヌは震えるほど嬉しかった。自分の体を美しいと言ってくれる、長年傷つけられてきた魂が癒される気がした。
だが、彼の顔がそこに近づこうとしたので口から出たのはまた彼を責める言葉だった。
「いやあっ、やめてったら! これ以上恥ずかしいことをしないでっ」
そんな行為をされたら、どれほど乱れるか分からない、そんな自分を見せたくなかった。
(お願い、私を淫らだと思わないで)
テオドールはリュシエンヌの悲鳴を聞いても彼女を開く力は緩めなかった。
「暴れないで、これはけっして恥ずべき行為じゃない。お前をたっぷり味わって、愛したいんだ。お前の体はまだ咲き始めたばかりで傷つきやすい。だから――」
彼の舌先が小さな花弁に触れた時、リュシエンヌの体がびくっと跳ねた。
「あっ……!」
声を出しそうになって慌てて口を押える。それほどその感触は甘美だった。
唾液で濡れた舌がもぞもぞと体の中へ入り込んでくる。自分でも知らなかった感触、罪深くて甘美だった。
「ああ、こんな、こんな……」
狭い間を何度も擦られていると、内から湧き上がってくるものがある。さっきから感じていた快楽の波がそこをじいんと熱くさせていた。
「いや、そこは」
そこをぬめぬめと責め立てられ、やがてひときわ感じやすい粒が膨れ上がってきた。彼の舌はそれを捉え、優しく包んで軽く吸い上げる。
「ひゃんっ!」
ちゅっと啜られるたび、全身がかあっと熱くなる。もう快楽を隠せなかった。リュシエンヌの白い肌は薄桃色に染まっている。
「ああ、そんな、そこが、こんな風になるなんて……! どうなるの、私、どうしよう……!」
うわ言のように喘ぐリュシエンヌの様子を見ながらテオドールは的確に快楽を与えていく。執拗に花弁をしゃぶりながら淫らな粒をちろちろと舌先で擦った。リュシエンヌの唇からそのたびにか細い悲鳴が上がる。
「ふわっ、ああ、もう、駄目……!」 -
関連作品